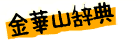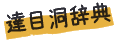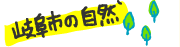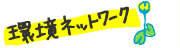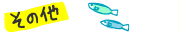8月3日(日曜日)、みんなの森ぎふメディアコスモスかんがえるスタジオで、令和7年度第1回岐阜市生物多様性シンポジウムを開催しました。
本シンポジウムは、生物多様性の保全などについて市民の皆さんと一緒に考えるイベントとして開催しています。
今回は、岐阜高等学校自然科学部生物班の皆さんに、外来種であるホソオチョウが在来種のジャコウアゲハにもたらす影響を事例発表していただきました。
また、名和昆虫博物館館長である名和哲夫さんからは、昆虫採集から生物多様性を理解することの重要性について講演していただきました。
・事例発表「堤防でチョウを2年間追い続けて分かったこと」
岐阜高等学校 自然科学部 生物班
岐阜市内の長良川堤防で2年間にわたり外来種であるホソオチョウが在来種のジャコウアゲハにもたらす影響について、様々な実験や調査の結果をもとに、発表していただきました。
実際に、成体数調査、マーキング調査、環境変化によるジャコウアゲハの体色の変化、食草であるウマノスズクサの分布、この4つの項目をもとに「生息状況は悪化しても、ジャコウアゲハは優れた生存戦略をもち、それらを乗り越えてきた」ということを、今回発表していただきました。

・講演「楽しい昆虫採集のすすめ」
名和昆虫博物館 館長 名和哲夫 氏
昆虫採集の方法やその楽しみ方について、自身の経験を交えながら、ご説明いただきました。
昆虫採集のコツについては、昆虫の下側にタモを置き、下から上へ一気にタモを振ると昆虫を採集しやすいと説明され、参加していた小学生の子たちから早速やってみたいと声が聞こえました。
また、昆虫の特徴や種類についてクイズ形式で教えていただき、老若男女問わず盛り上がりました。
ゴキブリやハエが昆虫である一方、クモやダニが昆虫ではないという話や、昆虫には3対の足があり、頭・胸・腹がはっきり分かれていることなど、新たに知ることも多く、驚きの声が多く聞こえました。
昆虫の理解を深めるためには、人間が昆虫と同じ土俵に立つことが大切だそうです。

・トークセッション
名和昆虫博物館 館長 名和哲夫 氏
岐阜高等学校 自然科学部 生物班
岐阜大学 応用生物科学部 岡本朋子 氏
トークセッションでは、コーディネーターとして岐阜大学応用生物科学部の岡本朋子さんに進行をしていただきました。岡本さんは昆虫に関する研究者であることから、ご自身の見識などを踏まえ、質問と回答について整理していただきました。
名和講師と岐阜高等学校自然科学部生物班の方々に、参加者の方々からいただいた質問にお答えいただきました。
<名和講師への質疑応答>
Q1 今まで採集した中で一番自慢できる昆虫は何ですか?
A1 印象的だったのはミヤマカラスアゲハですね。
Q2 死ぬまでに採集してみたい昆虫は何ですか?
A2 採集したい昆虫はたくさんありますが、環境省による規制のため、現実的には難しいものがほとんどです。我慢しています。
Q3 環境省による規制がなかったら採集してみたい昆虫は何ですか?
A3 ミヤマモンキチョウやフタオチョウです。
Q4 最近の地球温暖化は昆虫にも影響しますか?
A4 高山帯のチョウなどは、絶滅してしまう可能性があります。地球温暖化による影響だけでなく、人間の経済活動により、草原性のチョウの絶滅も危惧されています。
Q5 チョウは日本に何種類生息していますか?
A5 260~270種類生息しています。
Q6 世界には何種類生息していますか?
A6 17,000~18,000種類生息しています。
Q7 昆虫採集のおすすめの場所は?
A7 クワガタムシやカブトムシは樹液の多い樹にたくさんいます。例えば、伊自良川や長良川、揖斐川の近くにカワヤナギという樹があります。昼間にスズメバチがいるような樹はとてもいいです。
Q8 日本に生息するチョウで最も大きい種類はなんですか?
A8 オオムラサキ、モンキアゲハの夏型、オオゴマダラが最大級ですね。
Q9 標本はどのように作るのですか?
A9 いつ、どこで、だれがというデータがついていて、長持ちすることが大事です。長持ちさせるためには、とにかく乾かすことが大事です。名和昆虫博物館のホームページにも標本の作り方を載せているのでぜひ見てみてください。
<岐阜高等学校自然科学部生物班への質疑応答>
Q1 チョウのマーキングはどのように行っているのでしょうか?
A1 つかまえたチョウの種類と地点によって、色を分けてマーキングしました。例えば、A地点ではホソオチョウに水色、B地点ではジャコウアゲハに白色をマーキングしました。羽がすれて色落ちしないよう、広範囲にやさしく行いました。
Q2 ホソオチョウは外来種にもかかわらず、どうやって日本の中で生活範囲を広げてきたのでしょうか?
A2 主な要因として、人間によって、本来とは異なる場所で放たれたためではないかと推測しています。
Q3 ホソオチョウはどこで分布していますか?
A3 主に本州に分布しており、福島県から大分県に分布しています。