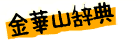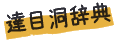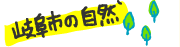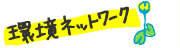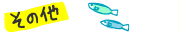令和7年5月22日(木)、畜産センター公園にて、NPO法人ふれあいの森自然学校の皆さんにより、椿洞ワクドキ自然散策会が開催されました。
この散策会は定期的に開催されていますが、今回も40人近くの参加者が集まり、前回に続いて、ふれあいの森自然学校の皆さんが驚くほどの盛況ぶりでした。

今回も大人数のため、2つのグループに分かれて散策することになりました。
-300x225.jpg)
最初に説明があったのは、ムクノキです。
ムクノキは、実はおいしくてホシガキのような味がするそうです。
このことは、もちろんヒヨドリなどの鳥も知っているので、食べごろになったら、すぐに食べられてしまうそうです。。
ムクノキは葉も利用価値が高く、爪を磨くこともできるとのことでした。
実際に参加者の人たちは、一生懸命、爪を磨いてました。


これはユリノキです。北アメリカ原産の外来種で、成長すると30m以上になります。
花はチューリップの花に似ているので、チューリプツリーとも言われているそうです。

続いて説明があったのは、トチノキです。
実は食べることができますが、食べれるようになるまで、大変、手間がかかるそうです。

-300x225.jpg)
トチノキにクスサンというガの幼虫がついていました。
このガはカイコのように繭を作りますが、壁面が網目状となるので、その繭は透かし俵とも呼ばれています。
-300x225.jpg)
別の場所に繭がぶら下がっていました。

これはテーダマツです。これも北アメリカ原産で高く成長する木です。
木材に利用するため、移入されたそうですが、今では利用されず、各地で生育しているそうです。


少し移動した後、ササユリの花を見ることができました。
このササユリは、徳山ダムがある場所から移植されたものとのことです。
-300x225.jpg)

別の場所で地面を見ると、小さな花が咲いていました。
黄色の花はブタナで、白い花はセッカニワゼキショウです。
ブタナはヨーロッパ原産、セッカニワゼキショウは北アメリカ原産の外来種とのことです。

これはキンランというランの仲間です。
半寄生といって、樹木のそばでないと生育できない珍しい植物です。

少し移動して、湿地周辺で生育する植物の説明がありました。
これはウシミツバです。ミツバという名前ですが、あまりおいしくないそうです。

これはドクダミです。ドクダミ茶などで有名ですね。
実は無毒で、薬用にも利用されています。

これはヤブジラミです。実が衣服にくっつきやすいです。

これはマムシグサです。名前からして怖そうな名前ですが、実際に有毒とのことです。
特に球根は毒性が強く、絶対に食べないように!とのことでした。

水際ではカキツバタの花が咲いていました。古来より親しまれている植物で、
平安時代の「伊勢物語」でも有名ですね。

カキツバタに似ているハナショウブの花も咲いていました。
ハナショウブは、カキツバタより、低地に生育するそうです。
ちなみに菖蒲湯の菖蒲とは、別の植物です。
-300x225.jpg)

湿地周辺から移動したら、また、地面に小さな花が咲いていました。
白い花はシロツメクサ、いわゆるクローバーです。黄色い花はコメツブツメクサです。
両方ともヨーロッパ原産の外来種で、江戸時代にガラスを守るための緩衝材として
使われたのでツメクサという名前がついたそうです。


北アメリカ原産のハルジオンの花が咲いていました。歌の題材としてもなじみがありますね。
ハルジオンに類似するヒメジョオンはまだ開花していませんでした。

これはハッカです。清涼感のある香りが特徴で、虫よけにも利用できるそうです。

ノアザミの花が咲いていました。食用にも薬用にもなるそうです。
とげがあるので、要注意です。

これはウルシです。かぶれるので、素手で触るのは厳禁です。

ウルシに似ていますが、これはヤマハゼです。これもかぶれるので、要注意です。

出発点近くに戻ってきたら、カシワの木に大きなヤママユガの幼虫が5匹!ついていました。
立派な繭を作るので、天蚕といって、生糸のために利用されていました。

今回の散策会は、これで終了です。
皆さん、お疲れ様でした。そして、ふれあいの森自然学校の皆さん、ありがとうございました。
次回の椿洞ワクドキ自然散策会は、6月26日(木)に開催予定です。
椿洞の生物多様性について、楽しみながらたくさんのことを学べるので、参加してみてはいかがでしょうか。
岐阜市環境保全課