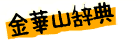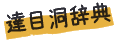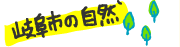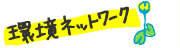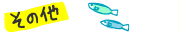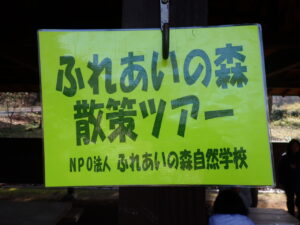令和7年2月16日(日)、ながら川ふあれあいの森にて、NPO法人ふれあいの森自然学校の皆さんにより、ふれあいの森散策会が開催されました。
この散策会は定期的に開催されており、通常は平日に開催されていますが、今回は久々に休日での開催となりました。
今回は「梅に鶯見たことある?」というお題のもと、ウメという名前が付いた植物をはじめとして、植物、鳥などについて解説がありました。
四季の森センターへ集合後した後、近くの三田洞弘法法華寺へ移動しました。
最初に境内に植えられている、しだれ梅について解説がありました。
しだれ梅は園芸種で、奈良時代に中国大陸から日本に伝わったそうです。枝を保持する力が弱いことから、枝が下がっていて、人が世話をしないと生育できないとのことでした。
例年、この時期には開花しているのですが、今年は寒波の影響からか、まだ蕾の状態でした。
次に、今回のお題である「梅に鶯」について解説がありました。「梅に鶯」は花札にも描かれています。
では実際に、「梅に鶯」を見たことがある人と確認したところ、1人だけでした。
実はウグイスは警戒心がとても強く、藪の中などに潜んでいて、人が見える場所にはほとんど出てこないとのことでした。
またメジロは花の蜜を求めて、梅に来ますが、ウグイスは昆虫などを餌としているため、特に梅を好んで来ることはないそうです。
それではどうして「梅に鶯」というかというと、梅の花もウグイスの鳴き声も春の訪れを告げるものとして縁起が良いため、組みあわせたのではないかということでした。
次に、同じく境内に植えられている、ロウバイについて解説がありました。ロウバイは漢字では蝋梅と書きます。
実はロウバイは梅という字が入りますが、実際は梅の仲間ではないそうです。梅はバラ科の植物ですが、ロウバイはロウバイ科の植物で、科のレベルで異なるとのことでした。ちなみにバラ科は植物の中でも大きなグループで、バラ、サクラ、モモ、ナシ、リンゴなど花がきれいで、果実を利用することができる種が多く含まれるとのことでした。
ロウバイは開花時期が早く、いい香りがします。当日も開花していて、参加者は順々に匂いを嗅いでいました。
次に解説があったのは、シキミです。シキミは葉の香りが良く、邪気を払うということで仏事に利用されるとのことです。しかしシキミは、アニサチンという毒を持つ有毒植物で、実を人が食べたりするのは厳禁とのことでした。
中華料理の香辛料である八角は、シキミの仲間であるトウシキミの実を乾燥させたもので、似ていることから、まれにシキミによる食中毒が発生するとのことでした。
ここで、境内を出て、ふれあいの森の中へ移動しました。
続いて、カツラについて解説がありました。カツラは「生きた化石」と呼ばれ、恐竜が生息していた白亜紀には生育していたことが分かっています。
イチョウのようにオスの木とメスの木があり、秋の紅葉時には甘い香りがするとのことでした。
この時期のカツラは冬芽がある状態です。冬芽はカニの爪のような面白い形をしています。
また枝にはメジロ?の巣が残されていました。
ここから、少し移動しました。
続いて解説があったのはビワです。果実を食べるのは言うまでもありませんが、葉も薬用などに利用できるとのことでした。
移動中、看板の下にマンリョウの実がなっているのを、講師の方が見つけました。鳥によって運ばれたようです。丸くて赤い実が特徴的で、類似する植物にヒャクリョウ、センリョウなどがあります。マンリョウは、それらの中でも実が大きくて、重いことからマンリョウと呼ばれるようになったのでは、とのことでした。
続いて解説があったのはシデコブシです。シデコブシは東海地方固有の植物で、岐阜市版レッドリスト2023では、絶滅危惧Ⅱ類に選定されています。
シデコブシも冬芽がある状態で、冬芽はたくさんの毛に包まれていました。
シデコブシの観察中、ヤマガラがすぐ近くにまで飛んできました。
写真はありませんが、鳥ではヤマガラ以外にシジュウカラ、メジロ、アオゲラなども確認できました。
続いて解説があったのはジャノヒゲです。7月、8月頃に開花し、根はバクモンドウという生薬に利用されるそうです。
ジャノヒゲにはきれいな青い実がなりますが、実はこれは実ではなく、種子だそうです。
続いて、冬季に開花するツバキとサザンカについて解説がありました。ツバキもサザンカも同じツバキ科ですが、花の落ち方や葉の形が違うとのことでした。
ツバキは花全部が落花しますが、サザンカは花びらが1枚、1枚落花するとのことです。また葉については、サザンカの葉は縁のギザギザがツバキの葉よりも大きいとのことでした。
こちらはサザンカです。ツバキとよく似ています。
ツバキとサザンカについて解説してくれた講師の方は、本当は鳥が専門で、花の蜜を吸うメジロの舌がどうなっているかも解説してくれました。メジロの舌はギザギザになっていて、花の蜜をからめとることができるそうです。
植物、鳥以外にも昆虫についても解説がありました。これはヤママユガの仲間のマユです。天蚕といって生糸がとれるそうです。
これは、ムネアカハラビロカマキリの卵のうです。ムネアカハラビロカマキリは、中国大陸原産の外来種で、近年、急速に生息範囲を広げているとのことでした。
今回の散策会は、これで終了です。植物だけでなく、鳥、昆虫などについても楽しく学ぶことができました。
参加者の皆さん、お疲れさまでした。そして、NPO法人ふれあいの森自然学校の皆さん、ありがとうございました。
ふれあいの森散策会は、6月~9月の暑い時期以外、毎月、開催される予定です。毎回、楽しく学ぶことができるので、参加してみてはいかがでしょうか。
岐阜市環境保全課